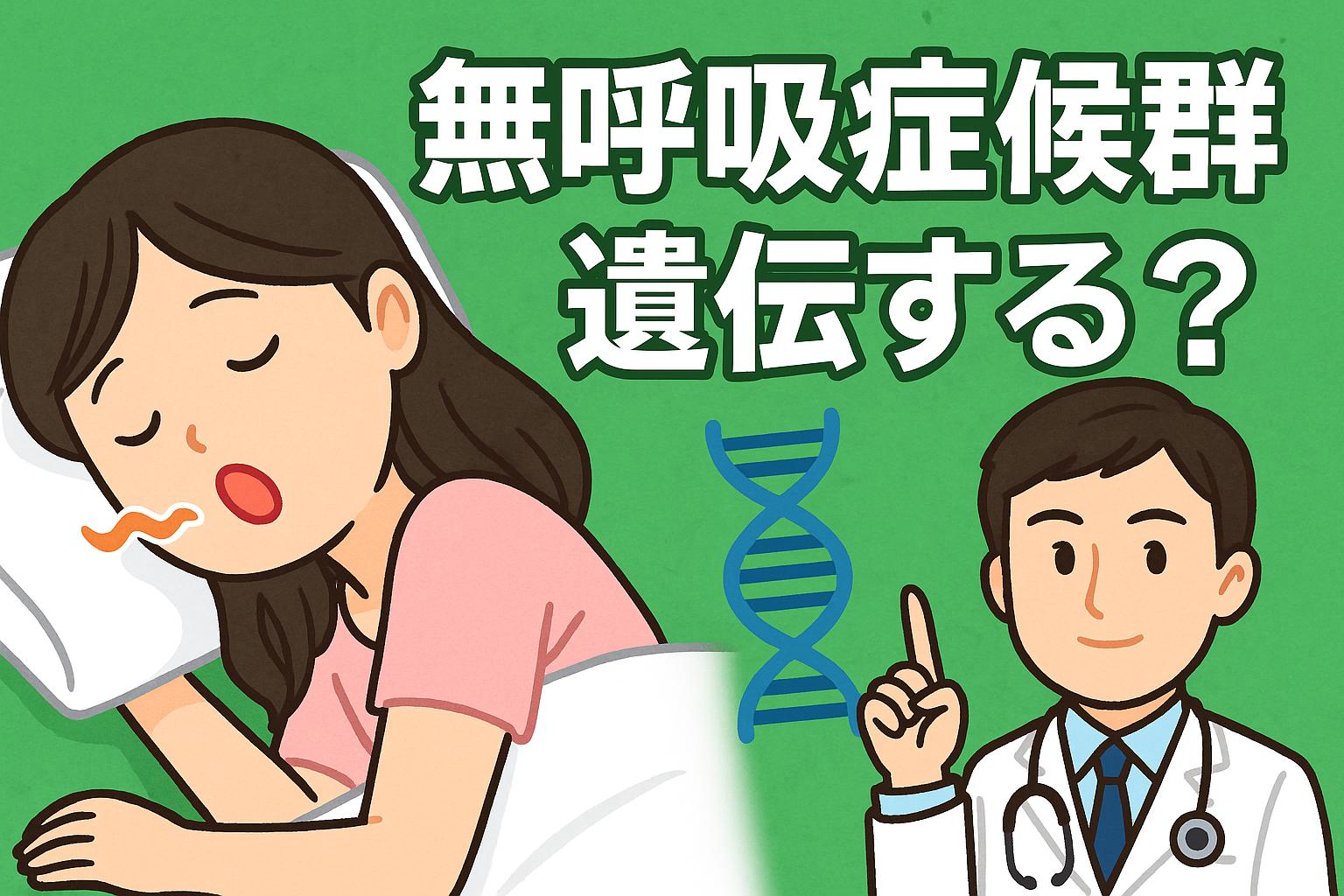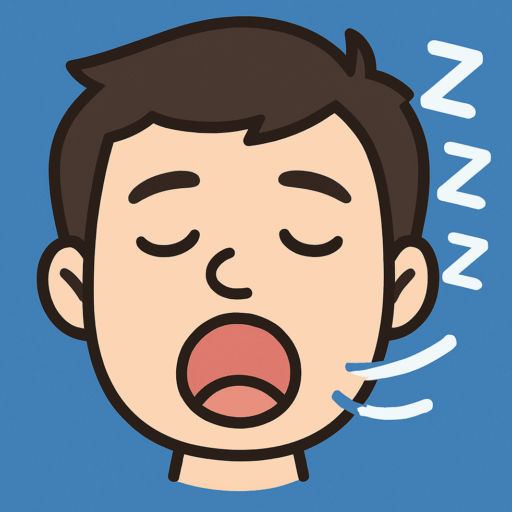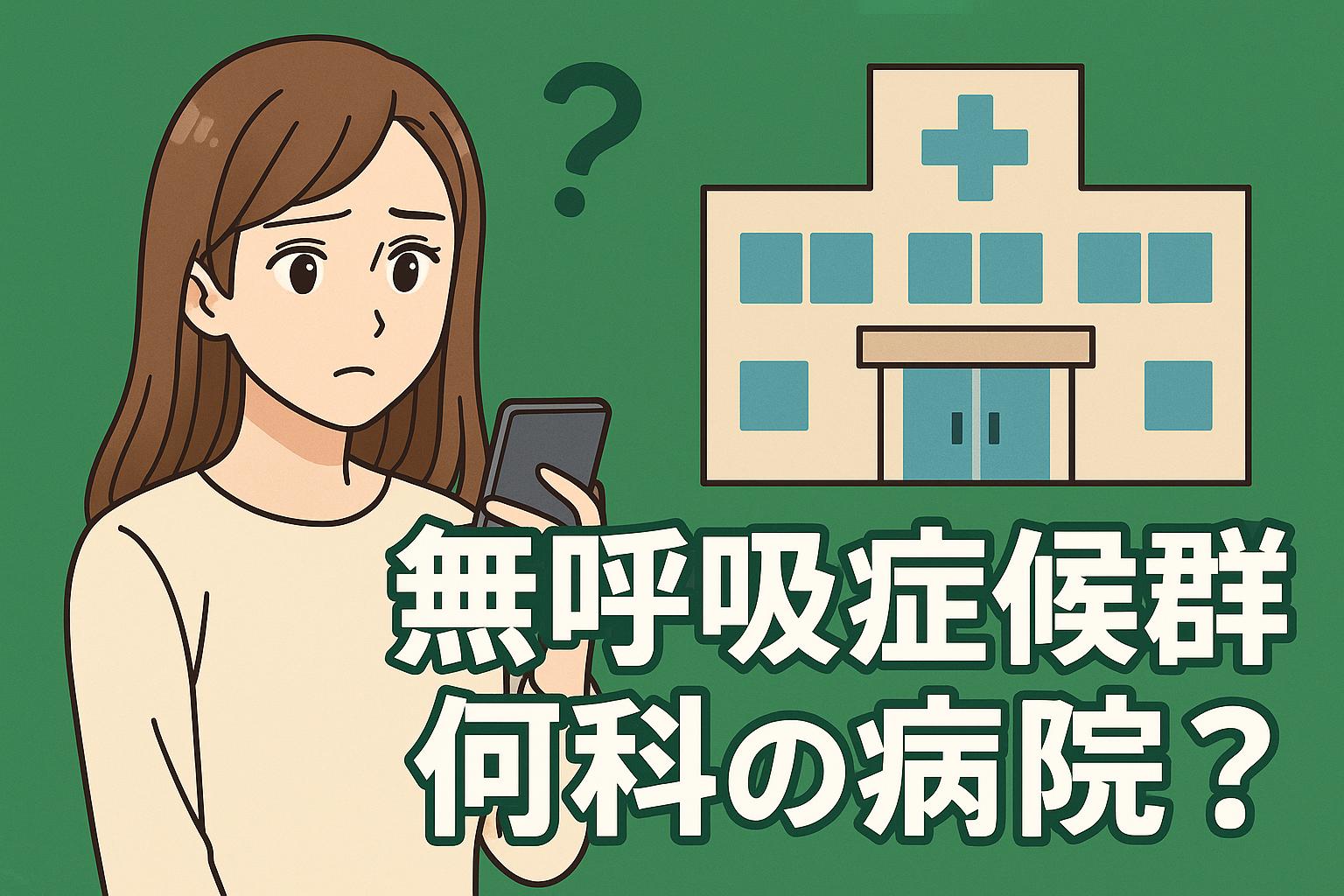
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に呼吸が繰り返し止まる、または浅くなる病気です。無呼吸とは、10秒以上呼吸が完全に止まる状態を指し、これが一晩に何十回、時には100回以上も起こることがあります。
本人の自覚が乏しいことが多く、最初に気づくのは同居する家族から「いびきがうるさい」「寝ていて呼吸が止まっている」と指摘されることがきっかけとなるケースが少なくありません。
SASには主に2つのタイプがあります:
-
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA):喉や気道が睡眠中に物理的に塞がることで起こる
-
中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA):脳から呼吸指令が出なくなることが原因
特に多いのは閉塞性であり、肥満、顎の小ささ、首回りの脂肪、扁桃腺の肥大などがリスク因子として知られています。
この病気の怖いところは、呼吸が止まるたびに睡眠が中断されるため、熟睡できず、日中に強い眠気や集中力の低下を招く点にあります。さらに、高血圧や心不全、糖尿病、脳卒中などの合併症を引き起こすリスクも高まるとされており、放置は危険です。
そのため、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合には、早期に病院で適切な検査を受け、診断をつけることが重要です。
問診とスクリーニング
病院で睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を受ける際、最初に行われるのが問診とスクリーニング(予備評価)です。これは、SASの可能性を見極めるための重要なファーストステップであり、患者の症状や生活習慣を詳しく確認することから始まります。
問診では、主に以下のような内容を聞かれます:
-
睡眠中にいびきをかくか、またその頻度や音の大きさ
-
家族などに「呼吸が止まっている」と指摘されたことがあるか
-
夜間に何度も目が覚めることがあるか
-
朝の頭痛やだるさの有無
-
日中に強い眠気を感じるか(特に運転中や仕事中)
-
生活習慣(喫煙・飲酒・肥満の有無など)
-
持病(高血圧・糖尿病・心疾患など)
加えて、エプワース眠気尺度(ESS)などのスコアテストを用いて、日中の眠気の程度を数値化することもあります。これにより、睡眠の質がどれほど影響を受けているかを客観的に把握できます。
この段階で医師は、症状や背景からSASの疑いがあると判断した場合、次のステップとして**検査の案内(簡易検査や精密検査)**に進みます。特に、いびき+日中の眠気がある人は要注意とされ、検査を強く勧められるケースが多くなります。
また、問診では一人暮らしで気づきにくい場合の対処法や、自覚がないケースにも対応できるように、必要に応じて睡眠記録アプリやスマートウォッチによる記録の相談も行われます。
このように、問診とスクリーニングは、医師と患者が一緒にSASの可能性を整理する大切な機会です。正直かつ詳しく話すことで、より適切な検査・治療につながります。
簡易検査(自宅で実施)
問診の結果、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがあると判断された場合、まず案内されるのが**簡易検査(スクリーニング検査)**です。これは自宅で行える検査で、自分のベッドで自然な睡眠をとりながらデータを収集できるのが最大のメリットです。
この検査では、以下のような測定が行われます:
-
酸素飽和度(SpO2):血液中の酸素濃度。無呼吸状態になると低下する
-
脈拍数の変動
-
呼吸の有無や回数(気流の検知)
-
いびきの音の記録(機種による)
-
体位(仰向け・横向きなど)
検査機器は、クリニックまたは病院から貸し出される小型の装置で、指先や鼻、胸部などにセンサーを取り付けて使用します。寝る前に装着して就寝し、翌朝回収または返送するだけなので、手軽かつストレスの少ない検査方法といえます。
ただし、簡易検査にはいくつかの制限もあります:
-
脳波などを計測しないため、正確な睡眠ステージ(レム睡眠・ノンレム睡眠)の把握は困難
-
無呼吸の重症度が軽い場合は見逃す可能性がある
-
中枢性無呼吸(脳の指令異常によるもの)は診断困難
そのため、簡易検査の結果で「無呼吸指数(AHI)が高い」または「判定が難しい」とされた場合には、より正確な終夜睡眠ポリグラフ検査(精密検査)に進むことが一般的です。
しかし、SASのスクリーニングとしては十分な信頼性を持ち、費用も比較的安価(保険適用で3割負担なら3,000~5,000円程度)なため、多くの病院では最初の検査として導入されています。
精密検査(終夜睡眠ポリグラフ検査)
簡易検査の結果で無呼吸の兆候が強く認められた場合や、より正確な診断が必要と判断された場合に実施されるのが、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG:Polysomnography)です。これは、病院や専門の睡眠センターに一晩入院して行う最も信頼性の高い検査方法です。
PSGでは、以下のような多岐にわたる生体情報を同時に記録します:
-
脳波(EEG):睡眠の深さやステージの判定
-
眼球運動(EOG):レム睡眠の検出
-
筋電図(EMG):あごや脚の動きの記録
-
心電図(ECG):心拍のリズムと変動
-
鼻や口の気流(呼吸センサー)
-
胸・腹部の動き(呼吸努力の測定)
-
血中酸素飽和度(SpO2)
-
いびき音と体位の変化
これらの情報をもとに、無呼吸の回数や長さ、低酸素の程度、睡眠の質、呼吸に伴う覚醒回数などを詳細に評価します。そのため、中枢性睡眠時無呼吸症候群や複雑性のあるSASの診断にも対応可能です。
検査は通常、午後から入院し、専用の個室または睡眠検査室で機器を装着したまま一晩眠ります。翌朝には装置を外し、医師が後日詳しい解析結果を説明する流れになります。
精密検査は、**健康保険が適用される場合(医師が必要と判断した場合)でも自己負担は1万~1万5,000円前後(3割負担)**とされています。ただし、病院によっては個室代などが別途かかることもあるため、事前の確認が重要です。
この検査により、睡眠時無呼吸症候群の重症度(軽症・中等症・重症)を客観的に判断し、その後の治療方針(CPAP・マウスピース・手術など)を決定するうえで不可欠な情報が得られます。
検査予約から結果説明までの流れ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いで病院を受診した場合、検査の流れは以下のようなステップで進みます。スムーズな診断と治療を受けるためにも、事前に流れを把握しておくと安心です。
① 初診(問診・スクリーニング)
まずは耳鼻咽喉科、呼吸器内科、または睡眠外来などで医師の診察を受けます。ここで症状のヒアリングが行われ、SASの可能性が高いと判断されれば、検査の提案を受けます。
② 検査予約の手続き
簡易検査であれば、その場で検査機器の貸し出し日を決定し、使い方の説明を受けます。精密検査(PSG)の場合は、病院内の検査室の空き状況を確認しながら、日程を調整します。検査の前に同意書の提出が必要な場合もあります。
③ 検査実施
-
簡易検査:自宅で一晩機器を装着して就寝、翌日以降に病院へ返却
-
精密検査:病院に一泊入院し、専用機器をつけた状態で睡眠
④ データ解析・結果待ち
検査が終わると、医師や専門スタッフが記録されたデータを詳細に解析します。この解析には通常1週間程度かかります(病院の混雑状況による)。
⑤ 結果説明・治療方針の決定
解析結果に基づいて、再診の際に医師から詳しい説明を受けます。無呼吸の頻度、重症度、睡眠の質などが明らかになり、必要に応じてCPAP療法やマウスピース、生活習慣の改善指導などが行われます。
このように、検査の予約から結果説明までは、早くて2週間〜1か月程度の期間が必要です。仕事や生活のスケジュールと合わせて、余裕を持って検査を受ける準備をしておくと良いでしょう。
検査にかかる時間・日数の目安
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を病院で受ける際、事前に知っておきたいのが検査に必要な時間や全体の所要日数です。検査の種類によって流れや所要時間が大きく異なるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。
簡易検査の場合
簡易検査は自宅で実施できるタイプの検査であり、病院での滞在時間は最小限です。
-
検査前の説明・機器受け取り:15〜30分程度
-
検査実施日:自宅で1晩(装着は就寝前に10分ほど)
-
機器返却と確認:10〜15分程度
-
結果説明の再診:5〜7日後(解析状況により異なる)
このように、通院は2回程度で済み、検査結果が出るまでのトータル期間は1〜2週間ほどが目安となります。
精密検査(終夜睡眠ポリグラフ)の場合
精密検査は病院や専門施設で1泊入院して行います。事前準備と検査当日のスケジュールは以下のようになります。
-
事前診察・予約:約30分〜1時間
-
検査当日:午後から入院、夜間に睡眠検査(約7〜8時間)
-
翌朝:装置の取り外し・帰宅(午前中に終了)
-
解析期間:約1〜2週間(混雑状況により前後)
-
結果説明の再診:検査日から10日〜2週間後
トータルで見ると、精密検査に関しては診察〜結果説明まで約2〜3週間程度の期間がかかることになります。
検査の所要時間まとめ表
| 検査の種類 | 所要日数 | 病院での滞在時間 | 通院回数 |
|---|---|---|---|
| 簡易検査 | 約1〜2週間 | 各15〜30分程度 | 2回 |
| 精密検査 | 約2〜3週間 | 1泊+診察各30分程度 | 2〜3回 |
検査の待機期間や解析時間は、病院の混雑状況や地域差によっても変動します。早期発見・早期治療のためには、気になった段階でなるべく早く受診し、スケジュール調整を行うことが重要です。
簡易検査と精密検査の費用比較
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を病院で受ける場合、気になるのが検査にかかる費用です。ここでは、保険診療で行われた場合の簡易検査と精密検査の費用感の違いを解説します。
簡易検査の費用
簡易検査は、自宅で1晩睡眠中の呼吸や酸素濃度などを測定するスクリーニング検査です。
-
保険適用あり(3割負担)の場合:およそ3,000円〜5,000円程度
-
※初診料や再診料を含めると、合計6,000円〜8,000円程度になるケースもあり
この検査は、手軽で費用も抑えられるため、最初のスクリーニング検査として非常に広く用いられています。
精密検査(終夜睡眠ポリグラフ)の費用
精密検査は、病院に一泊して脳波や筋電図、呼吸などを同時に測定する高度な検査です。
-
保険適用あり(3割負担)の場合:1万2,000円〜1万5,000円程度
-
※入院費(1泊分)や施設利用料が加わると、合計で2万円前後になることも
こちらは、検査内容が多岐にわたる分、費用も高くなりますが、診断精度が非常に高いため、治療方針の決定に重要な役割を果たします。
自費診療の場合は?
なお、医師の判断によらず自費で検査を希望した場合は、保険適用外となり、費用は2〜5倍程度になります。自費の場合:
-
簡易検査:1万5,000円〜2万5,000円前後
-
精密検査:4万〜6万円程度(病院により異なる)
保険適用の可否は医師の判断に基づくため、まずは保険診療で相談するのが一般的です。
保険が適用される条件とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査や治療には健康保険が適用される場合が多くありますが、そのためにはいくつかの条件や前提があります。保険を適用して検査や治療を受けるには、医療機関で適切な流れを踏むことが大切です。
1. 医師の診察を受けていること
まず第一に、医師の診察・問診を受けたうえで「検査が必要」と判断された場合に限り、健康保険が適用されます。自己判断で「不安だから検査だけしたい」と希望した場合は、自費扱いになる可能性が高いです。
2. 対象となる症状があること
以下のような症状があり、睡眠時無呼吸症候群が疑われると医師が診断した場合、保険適用の対象となります:
-
就寝中に呼吸が止まる・苦しそう
-
日中の強い眠気・倦怠感
-
集中力の低下
-
起床時の頭痛や口の乾き
-
高血圧や糖尿病との関連が疑われる
これらの症状が医師のカルテ上に記録され、医学的に必要な検査と判断されれば、保険適用が認められます。
3. 診療報酬の対象となっている検査であること
保険適用される検査は、診療報酬点数表に記載された正式な医療行為に限られます。簡易検査(自宅で行うスクリーニング)や精密検査(終夜睡眠ポリグラフ)は、いずれもその対象です。
ただし、検査後に行うマウスピース療法やCPAP療法も、保険診療として認められるためには診断結果に基づく必要があることを覚えておきましょう。
4. 医療機関が保険診療に対応していること
当然ながら、保険適用を受けるには、その医療機関が保険診療を行っていることが前提です。自由診療のみを行っている美容系クリニックなどでは適用されません。
まとめ:病院での検査で正確な診断と安心を得よう
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、自覚症状が少なく見過ごされやすい疾患ですが、放置すれば生活の質の低下や重大な合併症(高血圧、心不全、脳卒中など)につながる可能性があります。そのため、早期発見と適切な治療がとても重要です。
検査には自宅でできる簡易検査と、入院して行う精密検査があります。いずれも医師の診断に基づいて保険適用されることが多く、費用を抑えて正確な診断を受けられるのが利点です。検査の内容や流れは複雑ではありますが、この記事で紹介したとおり、数回の通院と1〜2週間の期間で結果が得られるケースが一般的です。
また、検査結果に応じてマウスピースやCPAP、生活習慣改善などの治療方針が決まります。自己判断で市販のいびき対策グッズに頼るよりも、まずは病院でしっかりと検査を受けることが、根本的な解決への第一歩となるのです。
「もしかして自分も……?」と少しでも気になった方は、ぜひ早めの受診を検討してみてください。正しい診断と適切な治療が、あなたの毎日の睡眠と健康を大きく支えてくれるはずです。
参考・引用記事
-
睡眠時無呼吸症候群の診断と治療について – 睡眠総合ケアクリニック代々木
https://www.suimin-clinic.jp/sas/about/ -
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査と治療|東京医科大学病院
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/clinical/otolaryngology/sas.html -
睡眠時無呼吸症候群とは?検査や治療、治療費用など – SOMPOヘルスサポート
https://www.sompo-hs.co.jp/column/sas/ -
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査内容と流れ|いびきメディカルクリニック
https://ibiki-medical.jp/treatment/